化粧文化研究者ネットワーク第70回研究会 ご報告
- kaogakunlcollab
- 2025年7月22日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年8月12日
2025年6月28日(土) 第70回研究会を開催しました。
■テーマ:「官能評価の歴史とこれから~食の場合から考える」
■講 師:早川 文代氏(農研機構 食品研究部門 食品流通・安全研究領域 分析評価グループ・グループ長補佐)
■日 時:2025年6月28日(土) 14:00~16:45
■会 場:資生堂汐留ビル
■形 式:対面とオンラインのハイブリッド
■講演概要:
講師の早川文代先生は、つくば市にある国立研究開発法人農研機構で、食品の官能評価法を研究されており、食品の官能評価法の開発や、それらの基盤となる日本語のテクスチャー用語体系の作成などに携わってこられた。
官能評価とは、人間の感覚器官をセンサとして対象物を評価する方法である。日本で食品の官能評価の記録が残っている最初の例は清酒で、1907年(明治40)に開催された第1回全国品評会での評価である。当時の評価基準は「色沢、香、味」の3つであった。
1960年には、旧食糧庁の主導で、米飯の官能評価をする上で指針となる「米の食味試験実施要領」が周知され、「外観」「味」「香り」「粘り」「硬さ」「総合」の6つが基準として示された。官能評価は、今では食品に留まらず、幅広い分野で取り入れられている。
一方、アメリカでは1936年に、物理的測定など科学的アプローチを導入した肉の柔らかさに関する官能評価が行われ、40年代には軍隊食の嗜好性研究のため官能評価が発展したという経緯がある。
1990年代以降、味覚センサ開発や分析機器の高度化により、「脱・官能評価」の風潮が一時あったが、2005年頃には「やはり人が評価しないとわからないことがある」と、官能評価は再評価された。現在、研究や製品開発にはスピードが重視され、官能評価にも迅速化が求められるようになった。また、AIによる官能評価の代替も期待され、そのための教師データとして、官能評価データの必要性が高まっている。
さて、食品の官能評価において重要なのは、評価の基盤となる感覚表現の整理である。特に、テクスチャー(食感)は用語を整理しておく意義が高い。用語の収集と分析については、1960年代の先行研究があるが、現代に合わせて再構築をするために、2003年に早川先生らによる用語の収集・整理が行われた。(用語の詳細は下記参照)
その総数は445語。この数は、中国語のテクスチャー用語リスト(144語)、英語(77語)、フランス語(221語)やフィンランド語(71語)と比べても、極めて多い。445語のうち約70%が「サクサク」「もちもち」「パリパリ」などの擬音語や擬態語であることや、「ねばねば」「ねっとり」など、粘りを表す言葉が多いことなども、日本語の特徴である。
その後の消費者を対象とした調査も含めて、テクスチャーに関する言葉には、文化圏・言語圏の食の特徴や、社会の変化、流行、男女差などさまざまな要素が反映されるのではないかと考えられる。
後半の質疑応答では、化粧品との比較をはじめ、多様な視点から意見交換が行われた。
食品同様、化粧品も外観、使用感(香りを含む)、使用後感などの官能評価は欠かせない。食品との違いは、食品は「食べるという行為を伴うため、人間の体全体がセンサとなって食品を評価する」のに対して、化粧品は「製品と皮膚の相互作用も含めて、製品、皮膚感覚のそれぞれが評価の対象となる」点にある。研究者によれば、今は人工皮膚なども使われるが、効果効能の評価においては、人の皮膚感覚が重要な意味を持つという。
また、消費者を対象にした用語認知度の調査において、食のテクスチャー用語の認知度が、2004年と2018年を比較すると減少傾向にある(約8割に減少)という点については、社会階層と食生活との関連、食育の重要性などにまで議論が広がった。
一連の議論を通して、収集・整理されたテクスチャー用語が、単なる言葉のリストではなく、私たちが生きている社会の一面を映し出していることを実感することのできた研究会だった。
(山村 博美)


.png)


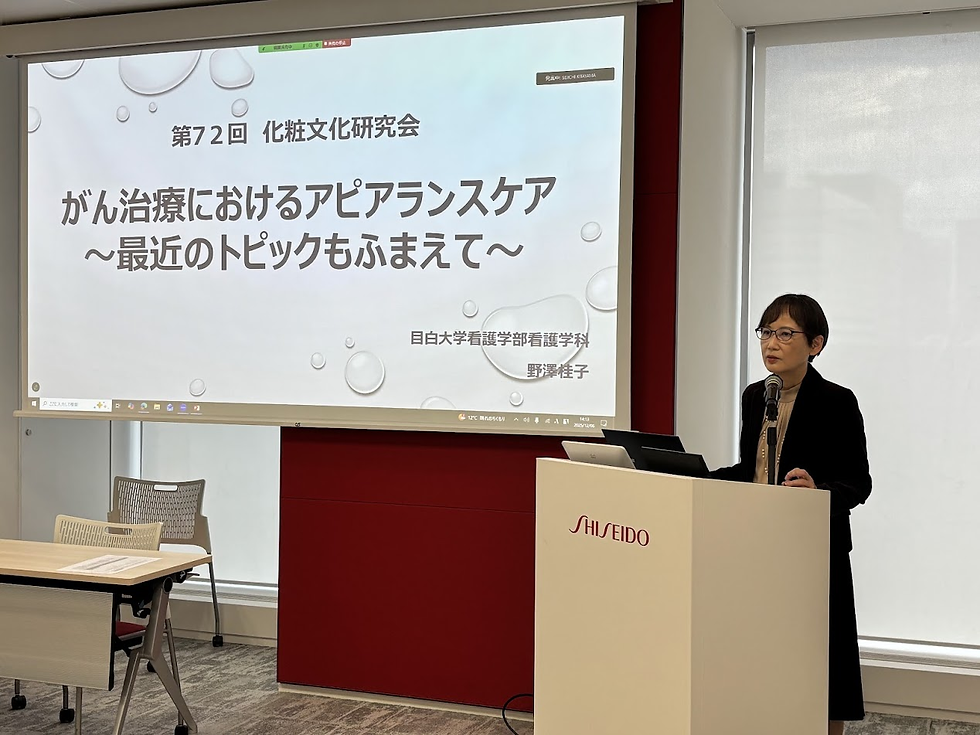



コメント