化粧文化研究者ネットワーク 第69回研究会報告
- kaogakunlcollab
- 2025年8月12日
- 読了時間: 3分
2025年3月17日、関西大学梅田キャンパスにて、第69回研究会が開催されました。
講演タイトル:ご著書『まなざしの装置 ―ファッションと近代アメリカ―』(青土社、2018/9/19)を中心にお話を伺う
■講演者:平芳 裕子(神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)
■日 時:2025年3月17日(月)
■会 場:関西大学梅田キャンパス701会議室
■形 式:対面とオンラインのハイブリッド
第69回研究会では,平芳裕子氏(神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授)をお招きし,『まなざしの装置 ―ファッションと近代アメリカ―』の内容を中心にご講演をいただいた。
ご発表の射程は北米の産業革命期から現代にまで及び,近代の女性像がファッションを通していかに成立し,変容してきたのかについて学んだ。本書は,雑誌や小説,パターン・マガジン,ショーウィンドウ,美術館展示といった多様なメディアを手がかりに,女性の装いがどのように社会的・文化的意味を帯びてきたのかを描き出している。単なる服飾史の叙述にとどまらず,ファッションが「女性的なもの」を構築し,社会規範として定着させる装置であったことを明らかにしている点が印象的であった。
中でも強く印象に残ったのは,第2章で扱われた「お針子」の存在である。産業革命期,衣服製造に携わる多くの女性労働者は低賃金・長時間労働に従事しながら,流行を形作る一翼を担っていた。しかし,その社会的評価は低く,女性像の形成においては「消費する女性」が前面に出る一方,「生産する女性」の姿は可視化されにくかった。この不可視性は,現代のファッション産業における縫製労働の状況とも通じるものであり,消費者としての私たちの視線の偏りを考えさせられた。
また,第3章で論じられていたパターン・マガジンの存在も興味深かった。雑誌付録として提供される型紙は,家庭の女性たちに流行の装いを再現する機会を与える一方で,その「模る」行為自体が流行の枠組みに組み込まれていた。これによりファッションは一見民主化したように見えるが,実際にはメディアが規定する理想像を再生産する過程でもあったという指摘は,現代のファッション消費の拡大とも結びつくものであった。
平芳氏の講演を通じ,資料収集への熱意と鋭い視点に深い感銘を受けるとともに,女性の「見る/見られる」関係が時代やメディアを超えて再生産され続けることの持続性に関心を抱くようになった。現代日本においても,雑誌やSNS,店舗ディスプレイが理想的な装いのモデルを提示し,それを参照・模倣する行為が日常的に行われている。私の専門とする文化心理学の視点からは,このような模倣と自己表現の相互作用が,アイデンティティ形成や規範維持にどのように寄与しているのかを検討する余地があると感じた。
今回の研究会を通じ,ファッションは単なる外見の装飾ではなく,社会や文化の中で規範を形成し,個人の生き方や価値観にまで影響を与える「装置」であることを改めて実感した。
(木戸 彩恵)

.png)


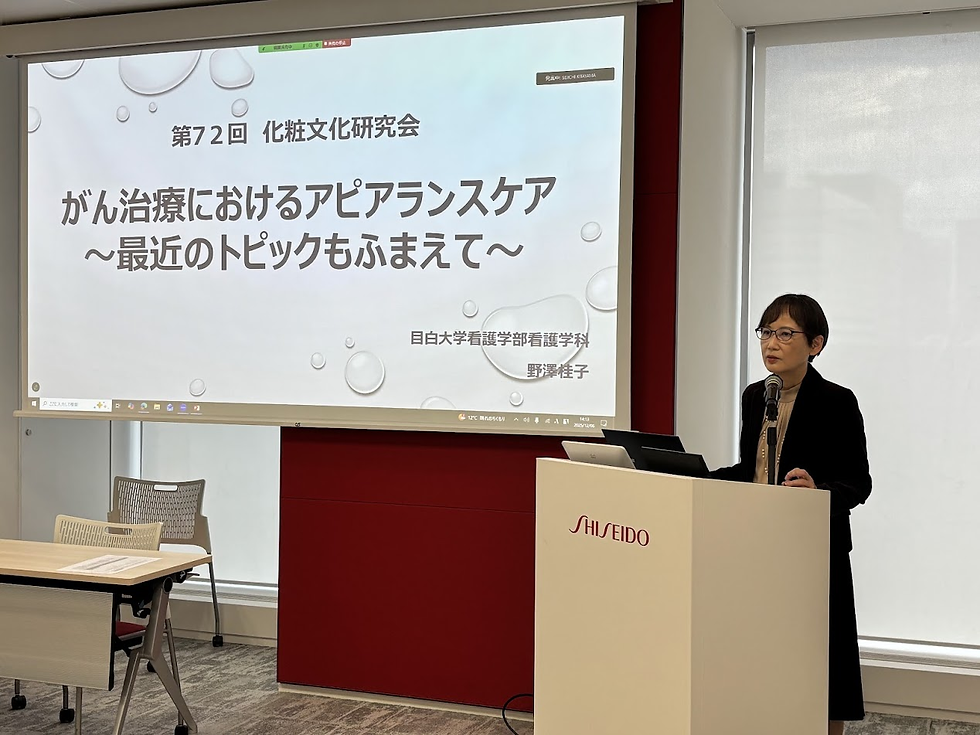



コメント